南極探検隊長白瀬矗顕彰会顧問 佐藤忠悦
北欧の極地探検時代、探検隊が、北方少数民族ラプラット人を帯同したことでもわかるように、極地探検には寒冷地に住む原住民と、彼らが飼っていた橇犬ハスキー犬を欠かすことはできない。南極点に到達したアムンセンは、この成功は「犬に始まり、犬で終わった」と断言するように、極地探検にはハスキー犬などの橇犬は重要な役割を果たしている。

白瀬南極探検隊は、当初蒙古馬を使用する予定であったが、探検船が縮小になったため急遽樺太犬に変更することになった。スコット隊が極地において主力の馬を全てへい死させたことを思えば、白瀬隊の樺太犬変更は、むしろ幸運といえるだろう。樺太犬使用によって、樺太アイヌ、山辺安之助と花守信吉が隊に加わることになる。
白瀬の南極探検の話が樺太(サハリン)に伝わってきたのは『あいぬ物語』によると「明治43年10月頃、トンナイ村の警察から犬30頭を土人が付き添って東京の南極探検隊に送るよう命じられた」とある。山辺(やまのべ)安之(やすのすけ)助はその役を担うことになるが、この大型犬を誰が使いこなせるだろうかと考えたとき、日本が世界の強国を相手にする南極探検に、少しでも力になりたいと思った。しかし村の人たちは山辺の南極行きに、必ずしも賛同したわけではない。彼は村民の信頼も厚く、将来を嘱望された人物であった。当時アイヌ民族は、偏見と差別によって、苦しい生活を強いられていた。「あいぬを救うのは、決して生易しい慈善などではない、宗教でもない、善政でもない、ただ教育だ」との信念のもと、山辺は漁場主の援助もあってアイヌの学校を建設する。南極探検に加わることも、自ら実践をとおしてアイヌ民族を見直してもらいたいう山辺の強い思いがあった。
もう一人のアイヌ隊員花守信吉は、敷香支庁の用務員をしており成富支庁長の信頼も厚く、どこに行くにも花守を帯同するという間柄だった。支庁長の強い勧めもあって、探検隊に加わることを決めている。
山辺が樺太犬20頭を引き連れ、犬たちと寝食を共にし、横浜に着いたのは11月5日。東京に来て、この南極探検は国の事業ではない事を知らされる。懇意にしていた金田一京助博士のところで、探検隊員を辞退してきたという地質学者から「南極に死に行くようなものだから、やめた方がよい」と諭されるが、「昨日承諾して、今日断ったら、やっぱりアイヌだなぁと下げしまれる。それは我慢できない」と決意を変えなかった。
明治43年11月29日、東郷海軍大将が命名した「開南丸」は東京芝浦から南極に向けて出航。山辺安之助と花守信吉は、「犬奉行」と言われ、犬の世話だけでなく帆の架け替え、甲板の清掃、学術部の手伝いなどあらゆる雑用を引き受け、陰ひなたなく働き、その勤勉さは、後に発行された『南極記』にも「両アイヌの常に勤勉、精励、忠実なるは、総員ひとしく感謝惜しむ能わざるところなり」と記している。
以下次号へ
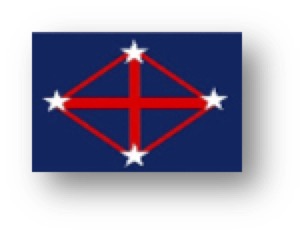
コメント