白瀬南極探検隊の計画が公になったのは、明治43年(1910)7月5日であった。当時東京神田にあった錦輝館の第一回発表演説会において一般に公表された。
この計画は当時著名な名士により賛助され、7月5日に南極探検後援会が組織され、大隈重信が会長となった。
国からの支援は受けられず、朝日新聞社の後援を受け、国民に義援金を呼びかけた。
白瀬隊の出航が遅れたのは、探検費用不足もさることながら、探検船がなかなか決まらなかったのが大きな原因であった。
色々と苦労した挙句に決まったのが「第二報效丸」という199トンの木造帆船であった。
「第二報效丸」は機関を据えて東郷平八郎(海軍元帥)が「開南丸」と命名し、明治43年(1910)11月29日、27名の隊員を乗せ、南極に向け東京港区芝浦を出航した。
明治44年(1911)2月8日、ニュージーランドで飲料水等を調達し、同月11日に出港した。
3月14日、ロス海コールマン島付近で氷海に前進を阻まれ、オーストラリアに引き返した。
5月1日、シドニーに入港、ウラーラ市で木造プレハブ小屋とテント生活で南極の夏を待った。
11月19日、数人の隊員の交代があったが、再び南極に向けシドニー港を出航した。
明治45年(1912)1月16日、午後10時、鯨湾(ホエール湾)に停泊。アムンセン(ノルウェー)のフラム号と出会う。
1月20日、白瀬隊長、武田学術部長、三井所衛生部長、花守、山辺の5名の突進隊が2台の犬ぞりで出発した。
1月26日「開南丸」は東方沿岸部を探検し南緯76度06分、西経151度20分の当時の最東端に到達した。
1月28日、突進隊は午後零時20分、南緯80度05分、西経156度37分に到達、日章旗を掲げ付近一帯を「大和雪原」(やまとゆきはら)と命名し最終到達地点とした。
2月7日「開南丸」は探検を終了し、鯨湾(ホエール湾)から日本に向け出航した。
3月30日白瀬隊長はシドニーから探検の事後処理のため「日光丸」で帰国した。(5月16日横浜着)
6月5日、小笠原群島父島の二見港に寄港。10日に出港。
6月19日、横浜港寄港。20日芝浦港に全員元気に到着し、大隈邸で歓迎式典が挙行された。 一行は、アムンセン(ノルウェー)やスコット(イギリス)のように極点征服はならなかったものの、204トンの木の葉のような木造機帆船で怒涛さかまく南氷洋を乗り切り、外国隊とは比較にならない貧弱な装備で南極に足跡を印したことは、当時の人々を大いに興奮させ、小さな日本人の大きな勇気と世界から賞賛された。
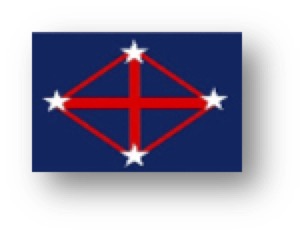
コメント